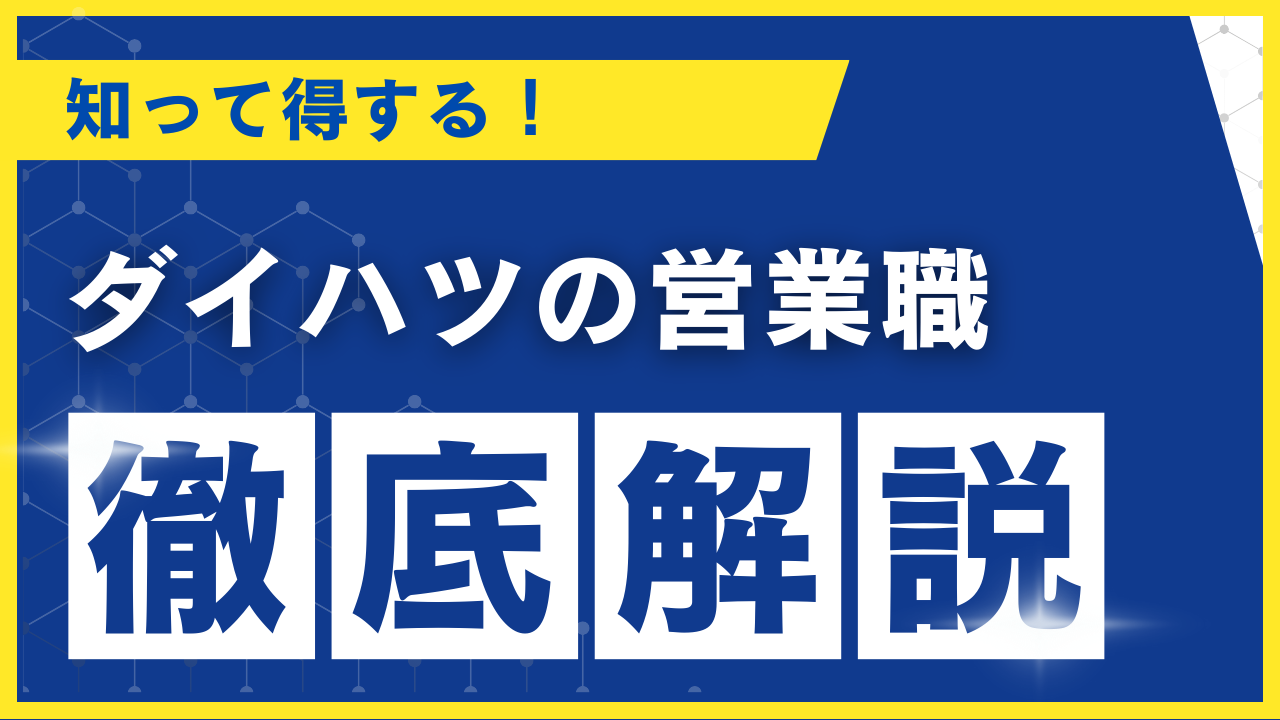「ダイハツの営業って大変?」「車の知識がなくてもできる?」「年収や将来性は?」——そんな疑問を抱く方は少なくありません。特に新卒や異業種からの転職を考えている人にとって、「車を売る仕事」には独特のイメージがつきまといます。
本記事では、ダイハツ営業マンのリアルな実態を徹底解説。仕事内容・きつさ・給料・キャリアパスまで細かく掘り下げ、成功するための行動習慣まで紹介します。
ダイハツの営業マンの仕事内容
業務の全体像
ダイハツ営業の仕事は、**「売って終わり」ではなく「売ってからが始まり」**です。新車販売はもちろんのこと、点検・整備・保険・ローン・リースなど、生活全般に関わるサポートを担います。
業務内容は大きく以下に分けられます:
- 集客対応:展示会やショールーム来店客の接客
- 商談:ヒアリング・車種提案・試乗案内
- 契約業務:ローン申請、保険加入、納車準備
- アフターケア:点検・車検案内、リピート提案
- イベント企画:フェア、試乗会、地域祭りなどへの参加
1日のスケジュール例
| 時間帯 | 主な業務 |
|---|---|
| 9:00〜 | 朝礼・進捗共有・清掃 |
| 10:00〜 | 来店対応・試乗準備 |
| 12:00〜 | 昼食・事務処理 |
| 13:00〜 | 商談・訪問営業 |
| 16:00〜 | 見積作成・契約業務 |
| 18:00〜 | 点検案内の電話・顧客フォロー |
| 19:00〜 | 翌日の準備・退勤(残業あり) |
繁忙期には20時過ぎまで残ることも珍しくありません。
直営店と販売会社の違い
- 直営店(ダイハツ工業グループ):給与水準が高く研修も充実
- 販売会社(地域ごとのディーラー):地元密着度が強く、家族ぐるみの付き合いが多い
ダイハツ営業の“きつさ”のリアル
① 数字に追われるプレッシャー
ダイハツ営業で最も多く語られる“きつさ”は、やはり販売ノルマに関するものです。
特に新車販売台数は、毎月5〜10台程度の目標が課されます。数字自体は大手トヨタ系ディーラーほど高くはないのですが、軽自動車という価格帯が比較的安い商品を扱うため、1件あたりの利益額が低めです。そのため、「台数で稼ぐ」スタイルになり、契約を積み重ねなければ目標を達成できません。
さらに、単純に“台数”だけを追えば良いわけではなく、
- 任意保険の契約率(ほぼ全件で提案必須)
- ローンやリース契約の推進率
- 車検や点検の誘致件数
- 紹介件数(1件でもあると評価が上がる)
など、複合的な評価指標があります。
数字が多面的に設定されるため、「今月は販売は好調でも、保険契約が伸びないから評価が低い」といったケースも発生します。営業マンは常に複数の指標を同時に意識する必要があり、そこに精神的なプレッシャーが加わります。
② 働き方のハードさ
営業は基本的に「平日休み」であり、土日祝はフル出勤。展示会やイベントも週末に集中するため、家族や友人との予定が合わせにくいという声が多く聞かれます。
- 残業:繁忙期には夜9時まで残業が続くことも珍しくない。
- 休日出勤:大型フェアや地域イベントで休日が潰れる場合あり。
- 繁忙期と閑散期の落差:決算期やボーナスシーズンは毎日のように商談が詰まり、体力的にかなりきつい。閑散期は逆に来店客が少なく、「どう数字を作るか」で頭を抱える。
さらに、地域密着型ゆえに「お客様の都合に合わせる文化」が強く、夜間や休日の訪問を求められるケースもあります。お客様の信頼を得るためには断りにくく、結果的にプライベートが削られるのも現場の悩みです。
③ 顧客対応の難しさ
自動車は生活に直結する商品です。購入金額も数百万円単位と大きく、契約時に慎重になるお客様が多いのは当然です。営業マンはその心理に寄り添いながら、契約につなげる必要があります。
- 「もう少し安くならないか?」という価格交渉
- 「他社と比較している」と言われ続ける駆け引き
- 契約直前のキャンセル
- 整備・修理での不満やクレーム対応
こうした対応は一件一件が重く、精神的にも消耗します。特に高齢者や家族連れのお客様が多いため、「説明が分かりにくい」と感じられるとすぐ不信感につながる点はプレッシャーです。
④ メンタル面での負担
数字に追われ、顧客対応に追われ、残業が続く——そんな日々が続くと、精神的に参ってしまう人もいます。実際にディーラー営業職の離職率は高めで、3年以内に辞めてしまう人も一定数います。
- 「毎月ゼロから数字を作らなければいけない」
- 「契約が取れないと社内で肩身が狭い」
- 「営業成績が給与に直結するため、生活の不安も増す」
一方で、数字が取れたときの達成感は非常に大きく、「やりがい」と「きつさ」が表裏一体で存在しているのがダイハツ営業の特徴です。
⑤ 他社営業との比較による“きつさ”の特色
- トヨタ・ホンダ系:法人営業や高額車種を扱うため、1件の契約単価が大きいが、競合も激しく、営業スキルが高く求められる。
- ダイハツ:契約単価は小さめで件数勝負。その分、接客回数が多く、体力面での負担が大きい。特に高齢顧客の割合が高いため、説明・サポートに時間を取られやすい。
つまり、ダイハツ営業の“きつさ”は「件数を積み重ねる体力勝負」「長時間労働による生活リズムの乱れ」「顧客の生活全般に寄り添う責任の重さ」に集約されます。
ダイハツ営業マンの年収・給料体系
① 平均年収の水準
ダイハツ営業マンの年収は、全国平均でおおよそ300万〜500万円のレンジに収まることが多いです。
もちろんこれは「全員が同じ」というわけではなく、勤務先(直営店か販売会社か)、地域差、個人の成果によって大きく変動します。
- 新卒1年目:月給20万円前後+歩合給少なめ → 年収280〜320万円程度
- 3年目:営業スキルが安定し、インセンティブも増加 → 年収350〜450万円
- 5年目以降:固定客・紹介客が増え、契約件数が安定 → 年収450〜550万円
- 10年目以上/トップ営業・管理職:実績次第で600〜700万円以上も可能
つまり「成果を出せば収入は上がる」が、「成果が出ないと基本給のみ」という現実もあるため、営業マン間での格差が大きいのが特徴です。
② 給料の仕組み(基本給+歩合給)
ダイハツの営業マンの給料は、大きく以下の2つで構成されています。
- 固定給(ベース給)
- 新卒初任給:月給18〜22万円程度
- 販売会社によって地域差あり
- 固定部分は生活できる最低ラインに設定されている
- インセンティブ(歩合給)
- 車1台販売につき数千円〜1万円前後
- 保険契約やローン契約で追加ポイント
- 紹介による成約は高額インセンティブが設定されることも
この歩合給がどれだけ積み上がるかで、年収は大きく変動します。
例えば「月10台販売+保険契約多数」なら、月5〜10万円のインセンティブが加わることも。逆に成績が低迷すればインセンティブはゼロに近づきます。
③ 直営店と販売会社での違い
- 直営店(ダイハツ工業の子会社)
- 基本給が高め
- 研修や福利厚生が充実
- 評価制度も体系化されているため安定感あり
- 地域販売会社(地元のディーラー)
- 基本給は直営よりやや低め
- インセンティブの割合が高いことが多く、成果次第で直営より稼げる場合も
- 社風はアットホームだが、店舗によって待遇差が大きい
就職・転職を考える際は、直営か販売会社かで年収の伸び方や福利厚生が大きく違う点を押さえておく必要があります。
④ 年収アップの現実的なシナリオ
営業マンが実際に「収入を増やしていく」にはいくつかのパターンがあります。
- パターン1:新規契約数で伸ばす
月10台以上を安定的に販売できれば、歩合給が大きく加算される。短期で一気に年収500万円台に到達可能。 - パターン2:紹介客・リピーターを増やす
既存顧客の紹介を安定的に獲得することで、新規営業の負担が減りつつ収入も安定。ベテラン営業に多いパターン。 - パターン3:管理職に昇進
店長・副店長クラスになれば役職手当が付き、年収は600万円台に乗る。数字だけでなくマネジメント力も求められる。
⑤ 他社ディーラーとの比較
- トヨタ営業:平均年収500〜600万円。法人契約や高単価車種があるためダイハツより高め。
- ホンダ営業:400〜550万円。契約単価は高いが競争も激しい。
- 日産営業:400〜550万円。インセンティブ制度は手厚いが、販売不振時の差が大きい。
- ダイハツ営業:300〜500万円。台数勝負だが軽自動車需要が安定しているため、実績を積めば安定収入に。
この比較からも、ダイハツは「大きく稼ぐよりも、安定して稼ぐ」スタイルに向いていることがわかります。
⑥ 年収と生活レベルの実感
実際に働く営業マンの声を聞くと——
- 年収350万円前後:一人暮らしなら問題ないが、家族を養うには厳しい
- 年収450万円前後:結婚・子育てをしながら生活可能。ボーナス次第で旅行や車購入も現実的
- 年収600万円以上:マイホームや教育費などの負担もこなせる安定ライン
つまり、3〜5年で年収450万円以上を目指せるかどうかがライフプランに直結します。
キャリアパスと将来性
① 営業職の基本キャリアステップ
ダイハツの営業マンは「売るだけの担当者」ではなく、成果に応じて着実に昇進できる仕組みがあります。一般的なキャリアの流れは以下の通りです。
- 営業スタッフ(1〜3年目)
- 来店客・訪問客対応
- 点検案内・フォローアップ中心
- 成績は波があって当然だが、誠実な対応が評価される
- 主任(3〜5年目)
- 一定の販売実績を出し、後輩の教育にも関わる
- 月間・年間目標を安定的に達成できるレベル
- 「売れる営業」として社内表彰されることも
- 副店長(5〜7年目)
- 店舗マネジメント補佐
- 新人教育や販売戦略の立案にも携わる
- 自分の数字+チーム全体の成果を意識する立場に
- 店長(7〜10年目以降)
- 店舗運営全体を管理
- 営業目標の設定・達成責任
- スタッフ採用や地域イベント企画なども担当
- エリアマネージャー・本部スタッフ(10年目以降)
- 複数店舗の統括
- 新規事業企画・法人営業・教育研修担当など
成果を出し続ければ、20代後半で主任、30代で店長、40代でマネージャーといった昇進も現実的に可能です。
② 営業以外のキャリアの選択肢
「営業として数字を積み続ける道」以外にも、ダイハツでは様々なキャリアが用意されています。
- 教育・研修担当:新人営業マンの指導係として育成を担当
- 本社スタッフ:商品企画・販促企画・営業戦略立案に関与
- 法人営業部門:企業や官公庁向けの大口契約を担当
- サービス部門との兼任:営業と整備を連携し、アフターサービス強化に携わる
つまり「ずっと売り続けるだけではキャリアが閉ざされる」ということはなく、本人の適性と希望次第で方向転換が可能です。
③ 実際のキャリアシナリオ例
例えば、次のような実例が考えられます。
- Aさん(新卒入社・30代前半)
→ 3年目で主任 → 7年目で店長 → 現在はエリアマネージャーとして3店舗を統括 - Bさん(中途入社・元アパレル販売員)
→ 営業で顧客満足度1位を獲得 → 本社マーケティング部門へ異動 → 新車キャンペーンを企画 - Cさん(新卒入社・女性営業)
→ 産休・育休を経て復帰 → 営業現場ではなく新人研修担当に → 社員教育の専門職としてキャリアを積む
このように、現場で結果を出せば出すほど、キャリアの幅は広がるのがダイハツ営業職の特徴です。
④ 将来性:自動車業界全体の変化とダイハツ
「これから自動車業界って大丈夫?」という疑問を持つ方も多いと思います。実際、EV化・カーシェア・若者の車離れなど、業界は大きな転換期にあります。
ただし、ダイハツには次のような強みがあります。
- 軽自動車の圧倒的シェア
- 日本国内では依然として軽自動車が圧倒的に人気
- 特に地方・高齢者層では「生活の足」として必須
- コンパクトカー市場の安定
- 維持費が安く、若年層・女性層にも根強い需要
- 「初めてのマイカー」として選ばれることが多い
- EV・ハイブリッド対応
- 小型EVの開発が進んでおり、今後はダイハツならではの低価格EVが期待される
- 地域密着戦略
- 大都市圏よりも地方での販売が強み
- カーシェアや自動運転が普及しても、「地域ディーラーでの信頼関係」は残り続ける
⑤ 営業マンとしての将来性
個人レベルで見ても、ダイハツ営業マンとしてのキャリアは今後も十分将来性があります。
- EV・安全技術の普及 → 営業は「機能を説明する役」から「安心感を届ける役」へ進化
- カーライフ全体の提案 → 車を売るだけでなく、保険・リース・カーケアサービスまで総合提案が必要
- 顧客との関係資産 → 1人の営業が築いた信頼は、AIやオンライン販売には代替できない
つまり、「車の販売員」から「カーライフアドバイザー」への進化が期待されています。
⑥ キャリアを活かした将来の展望
ダイハツ営業で培ったスキルは、他業界でも大きな武器になります。
- 金融業界(保険・ローン):資金計画サポートの経験が生きる
- 不動産営業:高額商品販売とライフプラン提案のスキルが応用可能
- 人材業界・教育業界:ヒアリング力・信頼構築力を活かせる
「営業力+信頼構築力」はどの業界でも通用する普遍的なスキル。仮に将来、車業界以外に転職することになっても、キャリアの選択肢が広がります。
⑦ まとめ:キャリアの魅力と将来性
- ダイハツ営業は 成果次第で20代後半から管理職を目指せる
- 営業以外にも 教育・本社企画・法人営業など多彩なキャリアが開ける
- 軽自動車市場は今後も安定し、EVや新サービス対応で成長の余地が大きい
- 個人としても「信頼構築力」「ライフプラン提案力」という 普遍的スキル が身につく
つまり、ダイハツ営業のキャリアは単なる「車を売る仕事」ではなく、将来の選択肢を広げる土台作りの場なのです。
未経験でも活躍できる?必要スキル
① クルマの知識はゼロでも大丈夫?
「車の知識がないと無理そう…」と不安になる方は多いですが、結論から言うと知識ゼロでも問題ありません。
実際、ダイハツの営業マンの多くは新卒で車業界に飛び込んでいますし、異業種からの転職者も珍しくありません。
なぜ大丈夫かというと——
- 研修制度が整っている:車種ごとの特徴、安全装備の知識、リースやローンの仕組みまで、入社後に学べる
- OJTが徹底されている:先輩営業に同行し、商談やアフター対応を隣で学ぶスタイルが主流
- マニュアルや提案ツールが豊富:パンフレット・シミュレーションソフトを活用すれば、細かな知識がなくても説明可能
つまり、「入社前に車に詳しい必要はない」けれど、「入社後に学ぶ意欲」は絶対に必要です。
② 本当に求められるのは“人間力”
ダイハツの営業マンが重視するのは、知識よりも人間的な魅力・誠実さです。
具体的には次のような力:
- ヒアリング力:「普段どんな使い方をされていますか?」と相手の生活を深く聞き取る
- 共感力:高齢者や主婦層が多いため、親しみやすく安心感を与える態度が重要
- 提案力:ライフスタイルに合ったクルマを自然に勧められる力
- 継続力:納車後も点検やシーズンごとの挨拶を欠かさず続けられる忍耐力
営業で成果を出している人ほど「クルマの説明よりも、お客様と世間話する時間の方が大事」と言います。
③ 成功する未経験者の特徴
実際に未経験からスタートして成功している人には、共通するパターンがあります。
- 素直さがある:先輩のアドバイスを受け入れ、改善を繰り返す
- フットワークが軽い:顧客からの電話にすぐ駆けつけ、信頼を積む
- 数字に一喜一憂しない:契約が取れなくても「次に繋げる行動」を淡々と継続
- 地道な努力が苦にならない:毎日の点検案内電話や挨拶回りを続けられる
特に「地道にやれるか」が大きな分かれ目です。派手なプレゼン力よりも、誠実にコツコツ行動する人が結果を残します。
④ 失敗する未経験者のパターン
逆に、早期離職してしまう未経験者にはこんな傾向が見られます。
- 数字へのプレッシャーに耐えられない:「今月もノルマ未達…」と焦りすぎて心が折れる
- お客様対応が苦手:クレームを恐れて行動が消極的になる
- 学ぶ姿勢が弱い:商品知識を後回しにして、説明できずに信用を失う
- 短期間で成果を求めすぎる:1〜2ヶ月で結果が出ず「自分に向いてない」と辞めてしまう
この仕事は「短距離走」ではなく「マラソン」です。最初は成果が出なくても、半年〜1年かけて顧客が増え、徐々に数字が安定していきます。
⑤ 研修制度と成長ステップ
ダイハツの販売会社や直営店では、新人育成に力を入れています。
- 入社時研修:商品知識、ローン・保険知識、接客マナー
- OJT研修:先輩営業同行で商談を経験
- 定期勉強会:新車モデル発表時の勉強会、営業ロールプレイング
- CS研修:顧客満足度向上のための接客スキル強化
成長ステップの目安:
- 3ヶ月目:先輩同行で小さな契約に関わる
- 半年目:自分で初契約を取れる
- 1年目:既存顧客フォローと新規契約を両立
- 3年目:紹介やリピーターが増え、安定的に成果が出る
⑥ 実際の現場エピソード
ある新卒営業マンは、最初の半年間1台も売れず悩んでいました。
しかし「点検の案内だけは欠かさない」と決めて毎日100件近く電話をかけ続けた結果、1年後には「点検からのリピート契約」で安定的に成果を上げられるようになったそうです。
別の中途営業マンは、「車に全く興味がなかった」ものの、顧客の趣味や生活スタイルの話を聞くのが好きで、自然に関係が深まり、3年目で店舗トップの成績を出しました。
つまり、クルマ好きである必要はなく、「人と向き合うことが好き」な人が強いということです。
ダイハツ営業マンが成果を出すための行動習慣
① 成果を出す人は“時間の使い方”が違う
営業職において「時間の使い方」は成果を大きく左右します。特にダイハツのように来店対応と外回りが混ざる営業では、**「受け身の時間」と「攻めの時間」**をどう配分するかが勝負の分かれ目です。
- 受け身の時間:来店客対応、試乗、契約業務など「顧客に対応する」時間
- 攻めの時間:電話・訪問・紹介依頼など「自ら仕掛ける」時間
成果を出す営業マンほど、受け身の仕事に流されず、攻めの時間を1日の中でしっかり確保しています。
② 朝の“仕込み行動”が鍵
ダイハツ営業マンの多くが口を揃えて言うのが、「朝の時間を制する者は成果を制する」という鉄則です。
おすすめのルーティン例:
| 時間帯 | 行動 | 意図 |
|---|---|---|
| 9:00〜9:30 | 前日の振り返り・当日の予定確認 | 商談の目的を明確化 |
| 9:30〜10:00 | アポ取り(電話・LINE) | 午前中のうちに予定を埋める |
| 10:00〜10:30 | 商談資料・下調べ | 提案の精度を高める |
午前中に「アポ・フォロー・準備」を仕込むことで、その日の商談成功率が大きく変わります。逆に、なんとなく朝を過ごす営業マンは、1日を受け身で終えてしまいがちです。
③ 目標を“分解”して管理する
営業目標は月単位で与えられることが多いですが、成果を出す人はそれをさらに細かく分解します。
例:月間10台販売の目標を立てる場合
- 週単位:2〜3台を売る計画に落とし込む
- 日単位:1日1〜2件の商談を必ず入れる
- 行動単位:「成約1件=商談5件」が必要なら、1週間に25件の商談を逆算
こうした逆算思考により「今日何をすべきか」が明確になり、日々の行動が数字につながります。
④ “信頼の積み重ね”を習慣化する
成果を出す営業マンほど、「売る」よりも「信頼を貯める」意識を持っています。
- 1日1信頼ルール:「今日1人の顧客から“ありがとう”をもらう」ことを目標にする
- 小さな約束を守る:点検案内の電話を忘れず、連絡すると言ったら必ずする
- 雑談力:世間話や趣味の話題を覚えておき、次回に繋げる
「売上=信頼の副産物」と捉える習慣が、紹介やリピーター獲得につながります。
⑤ 成功者と失敗者の“行動習慣の違い”
成果を出す人と出せない人の違いは、日々の積み重ねにあります。
| 成功者 | 失敗者 |
|---|---|
| アポ・訪問を午前中に固める | 午前中は雑務に流される |
| 目標を週単位で管理 | 月末に焦って行動する |
| 顧客との約束を必ず守る | 「忘れてました」が多い |
| 点検・整備で接点を増やす | 契約後フォローが疎か |
| クレームを前向きに処理 | クレームを避けて逃げる |
習慣レベルの差が、半年後には大きな成果の差として現れます。
⑥ 行動チェックリスト
毎日意識すべきチェックポイントをリスト化すると、行動がぶれません。
- □ 朝イチでアポ取りをしたか?
- □ 1日の商談目的を明確にしているか?
- □ 点検やフォローの連絡を欠かしていないか?
- □ 新規顧客だけでなく既存顧客にアプローチしたか?
- □ 今日は「1日1信頼」を積み上げられたか?
これを毎日振り返る習慣が、着実な成果につながります。
⑦ ケーススタディ:トップ営業マンの1週間
あるトップ営業マンは「1週間の行動ルール」を徹底していました。
- 月曜:既存顧客への点検案内を集中(信頼関係を固める日)
- 火曜〜木曜:新規商談・訪問を集中(攻めの日)
- 金曜:見積り・契約処理、翌週のアポ仕込み
- 土日:展示会・来店対応、商談のピーク
このサイクルを崩さずに回すことで、毎月安定して10台以上を成約。本人曰く「売れていない時期は“週のリズム”が崩れていた」とのことでした。
まとめ:ダイハツ営業の“リアル”と成功のポイント
ここまで、ダイハツの営業マンという仕事について「仕事内容」「きつさ」「年収」「キャリア」「必要スキル」「行動習慣」の6つの観点から解説してきました。最後に改めて全体を整理し、これから目指す人へのアドバイスをまとめます。
① 仕事内容の本質は「販売」より「信頼構築」
ダイハツ営業マンの仕事は、単に新車を売ることではありません。
- 新車販売
- 資金計画サポート(ローン・保険)
- 車検・点検案内
- アフターフォロー
- 地域イベント参加
など、顧客と長期的に付き合い続けることが軸です。**「売って終わり」ではなく「売ってからが始まり」**という意識を持てるかどうかが、仕事を楽しめるかどうかの分かれ目になります。