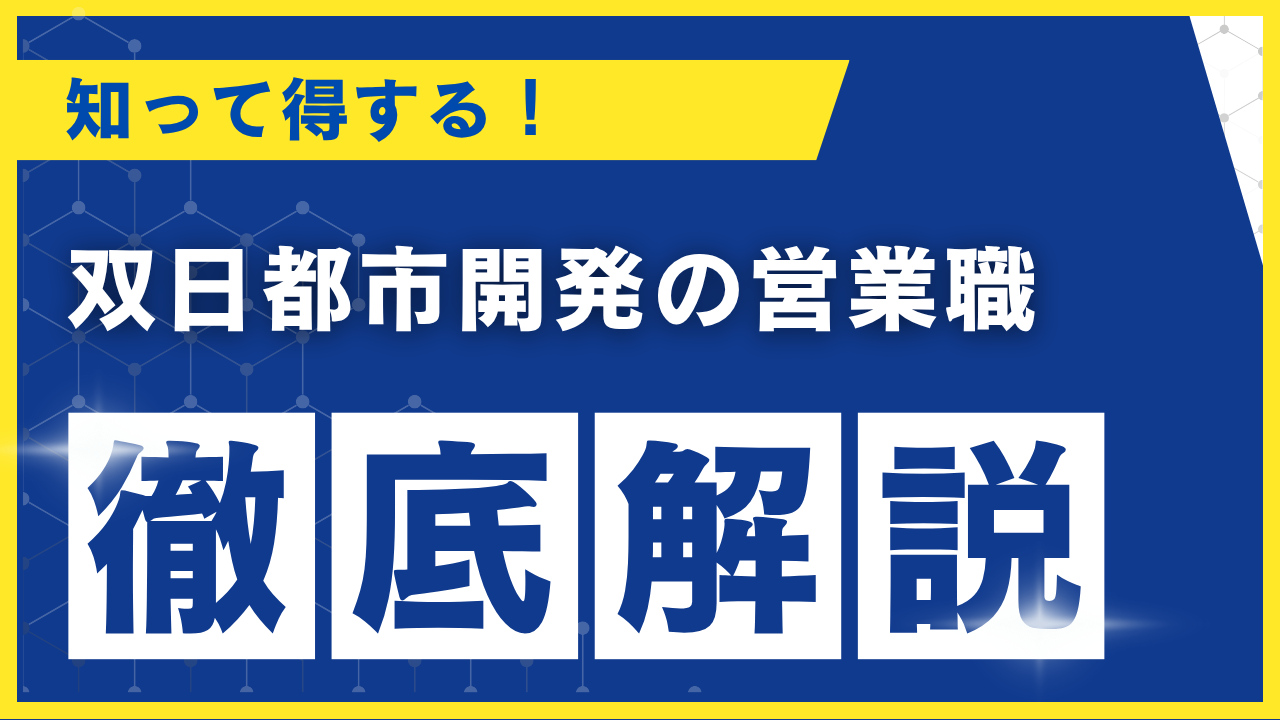新人でも結果が出せる営業スキルを、双日都市開発の営業文脈に合わせて体系化しました。この記事では、商談準備の要点から顧客ヒアリングの型、提案書の作り方、クロージングとフォローの運用までを、現場で使える順番で解説します。業界の一般的な成功法則をベースに、不動産開発の営業でありがちなボトルネックをどう解消するかに焦点を当てています。
読みどころは三つです。短時間で成果に直結する行動設計、顧客の意思決定を前に進める質問テンプレ、チームで再現できる営業プロセス管理。特定企業の内部情報に依存せず、どの現場でも通用する方法を提示します。今日から実践できるチェックリストと商談メモのフォーマットも用意しました。
結論のヒントです。勝ち筋はテクニックよりもプロセス設計です。小さな改善を日次で積み重ねる仕組みをつくれば、経験年数に関係なく成果は伸ばせます。この記事の手順を上から順に実行するだけで、商談の歩留まりが改善し、受注までの速度が加速します。
営業の全体像とゴール設定
最短距離で売上を積み上げるコツはプロセスを粒度まで定義することです。営業は運ではなく設計です。双日都市開発というキーワードで検索してくる読者が抱える典型課題は三つあります。案件発掘の母数が不足していること、商談が伸びて意思決定が遅いこと、提案の根拠が弱く収支に対する納得感が生まれないことです。ここをステージ分解して管理します。
パイプラインの段階定義
営業活動を五つの段階に分けます。見込み抽出、接点化、課題深掘り、提案合意、契約締結。それぞれで次の行動が明確になっている状態を合格とします。曖昧な感触はすべて未達扱いに寄せます。厳しめ判定が精度を上げる最短ルートです。
| 段階 | 合格条件の目安 | 次の一手 | 代表的な躓き |
|---|---|---|---|
| 見込み抽出 | 決裁者仮説と案件テーマが文書化 | 初回接点の打診 | ターゲットが広すぎる |
| 接点化 | 会話の約束と目的が合意 | ヒアリングの実施 | 特色のない導入トーク |
| 課題深掘り | 数値と期日で困りごとを特定 | 解決案の骨子整理 | 痛みが定量化できない |
| 提案合意 | 評価基準と比較軸を合意 | 条件交渉と最終案提示 | 提案書が厚いだけで要点不明 |
| 契約締結 | 稟議と契約条件の合致 | 署名日程の確定 | 条件変更の先送り |
表の合格条件はチェックリストで判定します。会話の温度感ではなく、文書や数字で確認します。
ゴールの置き方
月次の売上目標を立てる際は逆算の四層構造で考えます。受注金額、成約率、提案件数、商談化率の四つです。例えば成約率二割で月二件の受注を狙うなら、提案は十件、商談化は二十五件、接点化は五十件が目安になります。指標間の変換式を手元メモに固定しておくと、日々の活動が迷子になりません。
指標の最小セット
追うべき数字は三つだけでも機能します。新規接点数、提案化率、平均リードタイム。この三つが上がれば売上は自然に伸びます。指標は多すぎると行動が鈍ります。削る勇気が推進力を生むと覚えておいてください。
先に決める運用ルール
会議体や報告の型は最初に固定します。毎朝の十分単位の進捗確認、週次の案件レビュー、月次の失注分析を定例化します。ルールは短く回すほど効果が出るため、資料づくりに時間を掛けない方針を徹底します。フォーマットは後のセクションで配布します。
顧客理解を深めるヒアリング術
営業で最も成果差が出るのはヒアリングの深度です。表面的な質問では顧客の「本当の悩み」は見えません。双日都市開発のように複数部署が関与するBtoB営業では、意思決定プロセスが複雑です。だからこそ、聞く順番と切り口を意識的に設計することが成果に直結します。
ヒアリングの黄金比「7:3」
基本は顧客7割・営業3割の発話比率です。営業が話しすぎると信頼が生まれません。顧客が自ら課題を語り出した瞬間が最重要ポイント。ここで相手の言葉を使って要約+確認を返すと、信頼関係が一気に深まります。
例:「つまり、現在のテナント稼働率を上げるために、立地よりもリニューアル投資の優先順位を整理したいということですね?」
このように相手の意図を鏡写しにするだけで、「この人は理解している」と感じてもらえます。
深掘りの三段階質問モデル
ヒアリングは「現状 → 理想 → 障害」の三段階で構成します。
| 段階 | 目的 | 質問例 |
|---|---|---|
| 現状把握 | 事実を正確に知る | 「いまのプロジェクト進捗はどの段階でしょうか?」 |
| 理想把握 | 目標や成功イメージを明確にする | 「最終的にどのような街づくりを実現したいと考えていますか?」 |
| 障害把握 | ギャップを言語化する | 「理想に向かう中で、最大のボトルネックは何でしょうか?」 |
この三段階で質問すれば、会話の流れが自然に進み、顧客の“真の購買理由”が浮かび上がります。
数値を使って課題を定量化する
営業は感情のやりとりだけでは成約しません。必ず数字で課題を定義します。
たとえば、テナント誘致の課題を語る顧客には「目標稼働率」「現状稼働率」「空室の平均日数」を聞きます。数字で語ることで、提案の根拠が論理的に積み上がるのです。
また、双日都市開発のような都市開発営業では、ROI(投資対効果)を説明できるデータ視点が不可欠です。営業は数字の翻訳者であるべきです。
チームで共有するヒアリングメモの型
ヒアリング内容は個人の頭に留めず、チームで再現できるよう記録します。以下のフォーマットが有効です。
| 項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 顧客名・担当者 | 株式会社〇〇 事業開発部 部長A様 |
| 商談日・場所 | 10月5日 本社ミーティングルーム |
| 課題の整理 | テナント誘致のペースが目標未達(70%) |
| 成功条件 | 1年以内に稼働率90%以上を達成 |
| 提案ポイント | 既存ストック活用と新規開発のハイブリッド型提案 |
| 次アクション | 10月12日 ROIシミュレーション資料送付 |
このようにフォーマットを固定化することで、誰が見ても同じ文脈で顧客情報を共有できます。属人化を防ぐ最初のステップです。
「聞けない営業」を脱するコツ
「質問すると失礼かもしれない」と思って聞けない営業が多いですが、実際は質問しないほうが失礼です。顧客は自分のプロジェクトを理解してくれる営業を求めています。遠慮ではなく「共創のための質問」というスタンスで臨むと、関係が一気に変わります。
営業の強さは質問力の強さに比例します。双日都市開発のようなBtoB開発営業でも、最終的に決めるのは「人」です。人が心を開くのは、理解してくれる相手だけです。
提案書で信頼を勝ち取る営業プレゼンの作り方
営業が顧客に最も強く印象を残す瞬間は「提案書を提示するとき」です。双日都市開発のような都市開発系の営業では、提案書がそのまま企業の信頼性の証明書になります。内容の説得力だけでなく、構成・デザイン・話し方の順番まで設計する必要があります。
提案書の三層構造で理解を導く
良い提案書には共通点があります。それは構成が「戦略 → 数字 → ストーリー」で一本の筋道になっていることです。次の三層を意識して構成します。
| 層 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 戦略層 | 顧客の課題と解決方針を示す | 「何をするのか」を明確に伝える |
| 数字層 | 収支・投資回収・リスク分析などを数値で示す | 「なぜ実現できるのか」を裏づける |
| ストーリー層 | 成功イメージや将来像を描く | 「どう感じてほしいか」を動かす |
特に双日都市開発のように長期的な街づくりを扱う提案では、定量(数字)と定性(ビジョン)の両立が不可欠です。
提案書の冒頭で“時間を奪わない”構成をつくる
最初の3ページで、提案の全体像を10秒で理解できる設計にします。
読む人の多くは経営層やプロジェクト責任者であり、全ページを読むことはほぼありません。
したがって冒頭に以下の三要素を必ず配置します。
- 結論サマリー(「提案の骨子」を1枚にまとめる)
- 課題認識の一致(顧客の言葉で課題を再掲する)
- 成果イメージ(数字とイメージ図を組み合わせて示す)
この構成により、冒頭で「理解・共感・興味」が同時に得られます。
スライドデザインで差をつける三原則
- 1スライド1メッセージ
詰め込みすぎると、相手の理解が止まります。メッセージは1枚に1つ。 - 図で伝える構造化
開発計画やROI分析は、表よりも図解(マップ・タイムライン・フロー)で整理する方が早い。 - フォントと色は統一する
ブランド統一感は信頼感に直結します。フォントサイズも全ページで基準化。
営業トークは「順番」と「トーン」で決まる
プレゼンは資料よりも話し方の構成が命です。おすすめの順番は次の通りです。
- 背景の共有:「なぜこのテーマに取り組む必要があるのか」
- 課題の再定義:「現状の問題はここにあります」
- 解決方針の提示:「私たちの提案はこの方向性です」
- 成果の見通し:「実施後、どんな変化が起きるか」
- 次の一歩:「今日のゴールは合意ではなく、再検討への約束です」
顧客の頭の中で納得が積み上がる順番に沿って話すことで、提案が自然に「受け入れられる空気」を作れます。
失敗する提案書の特徴
営業現場でよくあるのが、「社内資料の焼き直し」です。
これは最悪です。顧客の課題を反映しない提案は、どれだけ見た目がきれいでも刺さりません。
他にも以下のようなパターンは要注意です。
- 専門用語が多すぎて理解できない
- 競合比較が抜けていて判断材料がない
- 提案の目的が途中でぶれる
- 「提案のための提案書」になっている
双日都市開発の営業現場では、開発スキーム・資金計画・自治体調整など多角的な視点が求められます。
だからこそ「何を伝えるか」よりも「何を削るか」を意識することが大切です。
提案後のフォローで差がつく
提案書を渡して終わりではなく、48時間以内のフォロー連絡が鉄則です。
相手のリアクションを確認し、「どの部分が引っかかりましたか?」と聞くことで、商談を前に進められます。
レスポンスの早さは信頼のシグナルです。遅い営業ほど、チャンスを逃します。
クロージングとフォローで成果を最大化する方法
営業が最も緊張する場面、それがクロージング(契約締結)です。
ここでミスをすると、何カ月もかけて積み上げた信頼が一瞬で崩れます。
しかし実際には、クロージングは「押す」行為ではなく、共に決断を確認するプロセスです。
双日都市開発のような大型案件では、関係者の合意形成が複雑ですが、仕組み化すれば確実に前進できます。
成約率を高めるための「決断支援型クロージング」
営業がやるべきは、「決めてください」と言うことではありません。
相手が意思決定できるように選択肢を整理し、リスクを見える化することです。
具体的な流れ
- 判断基準を整理してあげる
「収支」「スケジュール」「リスク」「関係者の合意」の4軸で比較表を作成します。 - 選択肢を2~3個に絞る
「A案:スピード重視」「B案:安全重視」「C案:バランス型」など。 - 顧客に“自ら選んでもらう”構造にする
営業が推すのではなく、「どの基準を重視されますか?」と尋ねる。
これにより、顧客の決定は自発的になり、後戻りリスクが減ります。
| 比較軸 | A案(スピード) | B案(安全) | C案(バランス) |
|---|---|---|---|
| 投資回収期間 | 2年 | 3年 | 2.5年 |
| リスク許容度 | 中 | 低 | 低中 |
| 施工コスト | 高 | 低 | 中 |
| 社内稟議の通りやすさ | △ | ◎ | ○ |
上記のように、判断の材料を可視化するとクロージングはスムーズになります。
クロージングを成功させる心理的フレーズ
営業トークでは、相手の思考を前に進める言葉選びが重要です。
- NG:「いかがなさいますか?」 → 判断を委ねすぎて停滞します
- OK:「こちらの方向性で進めても問題なさそうでしょうか?」
- OK:「ご懸念の部分が解消されれば、次の段階に進めますか?」
「Yes」ではなく「Not yet」を引き出すのがコツです。
断られた理由が明確になることで、次回提案の質が上がります。
フォローの黄金時間「48時間ルール」
提案・商談後48時間以内にフォローする。これは営業の鉄則です。
理由は単純で、顧客の記憶と熱量がまだ鮮明なうちに再接点を取るからです。
おすすめは以下のテンプレートです。
〇〇様、先日のご提案についての補足資料をお送りいたします。
ご懸念されていたROI算定の部分を、追加データで再計算いたしました。
来週中に一度、方向性の再確認をさせていただければと思います。
このように「追加の価値」を提供する形でフォローすれば、営業トーンが押しつけがましくなりません。
失注後フォローが「次の商談」を生む
多くの営業は、失注後に連絡を絶ちます。
しかし本当に強い営業は、失注フォローから次の案件を育てます。
たとえば、
「今回はタイミングが合わなかった」
「社内事情で見送りになった」
――こうした理由は、将来的なチャンスの予告にすぎません。
失注後に行うべき行動は次の3つです。
- 失注理由を記録する(感情ではなく事実ベースで)
- 半年後の再接点をカレンダーに登録する
- 「その後どうなりましたか?」の連絡を入れる
こうした地道なフォローが案件再浮上率を倍増させます。
双日都市開発のような長期プロジェクト型営業では、“種まき営業”こそ最大の武器です。
チームで成果を共有する習慣
営業個人の勝ち負けではなく、チーム全体でナレッジを循環させる仕組みが重要です。
おすすめは「週次レビュー会議」を質問ベースで設計することです。
質問例:
- 今週、一番響いた顧客の言葉は?
- 商談中に困った質問は?
- 次に改善したい提案ポイントは?
この問いかけを共有することで、チームの営業力が一段上がります。
営業スキルは共有した瞬間に再現性が生まれるのです。
最新トレンドに学ぶ双日都市開発型の営業戦略
都市開発領域の営業は、従来の「訪問・提案・契約」という直線型モデルから、共創・協業・伴走型営業へと進化しています。
特に双日都市開発のようなデベロッパー系企業では、営業担当者が単なる販売員ではなく、プロジェクトデザイナーとして機能することが求められます。
ここでは、2025年以降の都市開発営業における主要トレンドを整理します。
トレンド① データドリブン営業の加速
これまでの営業は「経験と勘」で進められてきました。
しかし今は、案件データ・市場データ・顧客行動データを組み合わせた精緻な営業判断が可能です。
たとえば双日都市開発では、
- 開発候補地の周辺人口動態データ
- 企業誘致履歴
- 建設コスト指数
などを統合分析し、「提案可能性が高い案件」を自動抽出する動きが進んでいます。
営業はこのデータを基に、「どの案件にどれだけ時間を投資するか」を最適化する時代です。
| 活動領域 | データ指標 | 活用目的 |
|---|---|---|
| 案件開拓 | 潜在需要スコア | 優先顧客を絞り込む |
| 提案準備 | 顧客課題パターン分析 | 提案書の精度向上 |
| 商談進行 | ヒアリングログ解析 | 成約確率の見極め |
| フォロー | 過去案件トラッキング | 再提案のタイミング予測 |
「データが営業を導く」構造を整備することが、売上を安定化させる鍵です。
トレンド② パートナー営業の拡張
都市開発は単独では成立しません。
自治体、不動産会社、建設業者、設計事務所、地域企業など多数のステークホルダーが関わるビジネスです。
このため、最近では「パートナー営業」という考え方が重視されています。
営業は顧客だけでなく、協力企業も“顧客”とみなす必要があります。
提案の初期段階で「誰と組むか」を明示することにより、交渉スピードと信頼形成が劇的に早くなります。
また、パートナー営業ではWin-Win構造の設計が重要です。
以下のように整理しておくと、提携先への提案も通りやすくなります。
| 相手 | 相手のメリット | 自社のメリット |
|---|---|---|
| 建設会社 | 継続的な案件受注 | 品質・納期の安定化 |
| 地域企業 | 雇用・経済効果 | 地元との信頼構築 |
| 金融機関 | 安全な投資案件 | 資金調達の安定化 |
営業が全体設計者としてハブになること。これが新時代の営業像です。
トレンド③ ESG・サステナビリティ志向の高まり
2025年以降の都市開発営業では、ESG(環境・社会・ガバナンス)視点が必須になっています。
企業が土地開発や再開発を進める際、単なる収益性だけでなく、
「地域貢献性」「環境配慮」「持続可能な運営体制」が問われます。
双日都市開発でも、再開発プロジェクトでの営業提案にカーボンニュートラル・省エネ性能・地域活性化の指標を織り込む流れが強まっています。
営業担当者がこうした社会的価値を数字で語れるようになると、企業の信頼は格段に高まります。
トレンド④ AIと営業プロセス自動化
AIは営業の敵ではありません。
むしろ、営業を“人にしかできない領域”へ集中させる味方です。
例えば以下のような業務がすでに自動化されています。
- 顧客データの整理
- 提案書のフォーマット生成
- 商談ログの要約
- 顧客への次回アクション提案
これらを活用することで、営業は「会う」「話す」「決める」という本質業務に集中できます。
AIを導入した企業では、商談回転率が20~30%向上するというデータもあります。
営業は“AIと共に動くプロジェクトマネージャー”として進化するのです。
トレンド⑤ 「信頼資本」が最強の武器になる時代
どれだけデジタル化が進んでも、最終的に顧客が選ぶのは「信頼できる人」です。
都市開発のように金額も期間も大きい商談ほど、
「この人と一緒に進めたい」と思わせる信頼が決め手になります。
信頼は「約束を守る」「スピードを保つ」「誠実に伝える」――この三つの積み重ねです。
どれも派手ではありませんが、営業の本質は“人の信頼を設計する仕事”だということを忘れてはいけません。
トレンドの総括
- データで動く営業が主流化
- パートナー連携が成果を決める
- ESGと社会価値が営業の新しい指標
- AIが営業の補助エンジンに
- 最終的な差は人間力(信頼資本)で決まる
双日都市開発の営業スタイルをモデルに考えると、これら五つのトレンドをどう融合させるかが今後の競争優位のカギになります。
まとめ
ここまで、双日都市開発の営業スタイルを軸にした「成果が出る営業の全体設計」を解説しました。
この記事の要点を整理すると、営業で成果を上げるための本質は次の五つに集約されます。
- プロセスを分解して見える化すること
感覚ではなく構造で管理する。これが成果の第一歩です。 - ヒアリングで顧客の“本音”を引き出すこと
課題を数字で捉え、相手が自ら話し出す空気をつくる。 - 提案書は“短く深く”構成すること
結論・根拠・ビジョンの三層で説得力を構築する。 - クロージングは押すのではなく支援すること
意思決定を助け、リスクを整理して共に決断する。 - トレンドを読むことで次の一手を先回りすること
データ、パートナー、ESG、AI、信頼資本。営業の軸はここに集約します。
営業は「話す」仕事ではなく、「仕組みを動かす」仕事です。
双日都市開発のような大規模プロジェクト型の営業ほど、
一つの行動改善が売上全体を動かすレバレッジになります。
そして何より、
営業の武器は自分自身の信頼と行動スピードです。
どんなに時代が変わっても、この2つが強い営業をつくり続けます。
今日からできることは、まず「自分の営業プロセスを紙に書き出す」こと。
構造化できた瞬間から、営業は再現性を持ち、チームで共有できる知識になります。
それが、次の成約を最短で生むスタート地点です。